ヒルマ・アフ・クリント展@東京国立近代美術館
- 西村 正

- 2025年6月13日
- 読了時間: 2分

スウェーデンの女性画家 ヒルマ・アフ・クリント(1862—1944)の日本初の回顧展が竹橋の東京国立近代美術館で開催中(2025.3.4~6.15)だ。日本初どころかアジア初だという。



ヒルマ・アフ・クリントは1862年にスウェーデンに生まれた女性である。1862年は日本で言えば文久2年。明治維新まであと6年という幕末の頃である。我が叔父・西村俊郎の生年より47年も前だ。20代の作品「夏の風景」を見ると、いかにも正統な具象絵画という感じで何の違和感もないが、その後の作品「大きな樹」あたりから、やや抽象的とも言えそうな要素が作品の中に見られるようになる。美術史で抽象画の始祖とされているのはカンディンスキーやモンドリアンのようだが、クリントの作品が抽象画であるとするなら、それは彼らよりも数年早いのだという。しかし本人の遺言によって、死後20年間作品が非公開とされたこともあって、その作品は正当な評価を受けてこなかったようだ。
私の感想は、「実に不思議な絵である」ということに尽きる。クリントは神智学、そしてのちにはルドルフ・シュタイナー(1861—1925)の人智学に傾倒して、シュタイナーとも面識があったようである。シュタイナーの名は日本では「シュタイナー教育」によって知られていると思うが、私も教員の仕事を始めた頃、『ミュンヘンの中学生---シュタイナー学校の教室から』(子安美知子著、朝日新聞社、1980年)などを熱心に読んだことがあった。
西村俊郎は画家としての人生において作風が抽象に向かったことは一度もなかったし、私も抽象画を好んで観るという嗜好を持ったことがなかったからかもしれないが、ある年配の知人が定年退職後に趣味として油絵を習い始めて数年のうちに具象から抽象に画風を変えてしまい、本人としては油絵をひと通りマスターしたと満足気だったのを見て、私は何とも割り切れない気持ちを味わったことがあった。念のため言っておくと、私は決して抽象画を否定するものではない。ただ、西村俊郎と同時代、さらにはクリントのように、もっとずっと以前の画家たちの中に、熱意を持って抽象絵画に打ち込んだ画家がいる一方で、どうして西村俊郎は生涯その画風を変えることがなかったのか、という関心は私の中にずっと眠り続けている。 (2025.6.13)
※本稿のクリント作品についての解説部分は、美術評論家アライ=ヒロユキ氏による記事(「しんぶん赤旗」2025.5.2号の文化欄に掲載)を参考にしています。


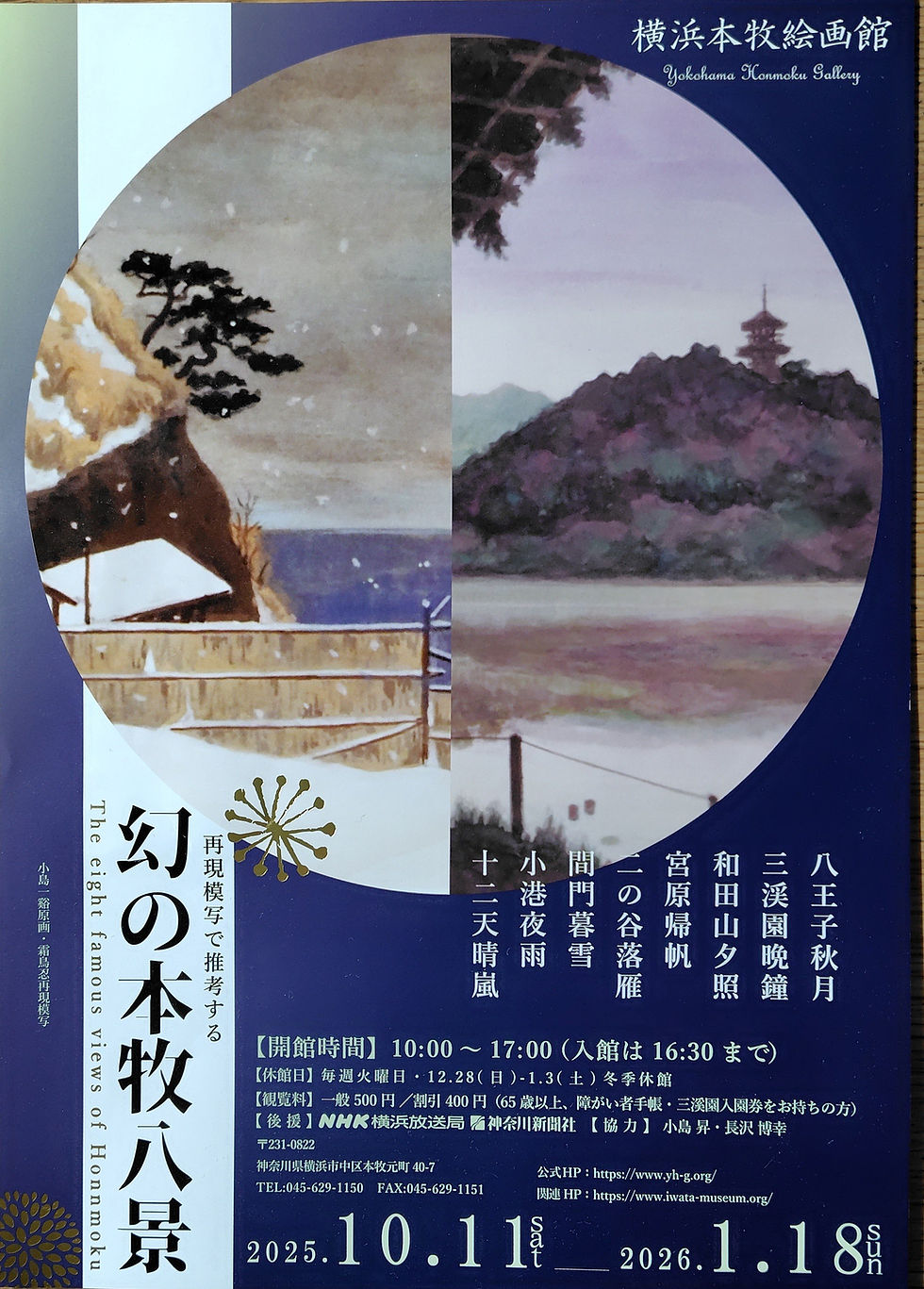

コメント