画廊のこと(その1)
- 西村 正

- 2023年10月23日
- 読了時間: 2分
私はこのところ、いくつかの画廊に繰り返し通うようになった。考えてみれば叔父・西村俊郎は、私が知る限り、画廊というものに全くと言っていいほど縁がなかったように思う。出入りの画商はいたが、展覧会と言えばデパートの美術画廊に決まっていた。だから絵を見る場所・見せる場所として美術館があることは勿論知っていたが、画廊というものには馴染みがなかったのである。私が画廊の魅力を知ったのは友人のお蔭である。知ってみれば画廊というものは何とたくさんあることか。しかも、それぞれに個性があって魅力的である。
というわけで、最近私がよく行くようになった画廊のいくつかを紹介したいと思う。まずはシェイクスピア・ギャラリーから始めよう。

東京は御茶ノ水、日本のカルチエ・ラタンたるこの街の明大キャンパスの裏手に佇む半地下風のおしゃれな画廊----それが「シェイクスピア・ギャラリー」に初めて行ったときの印象であった。この名前はパリの書店「シェイクスピア・アンド・カンパニー」に因むもの。「芸術監督」を称する清水篤さんの拘りと思い入れが感じられる。清水さんは月刊文化情報誌「本の街」に連載エッセイも執筆する。私がこの画廊に何回も足を運ぶ理由はいくつかあるが、企画のテーマがユニークで、つい心を惹かれてしまうということが大きい。
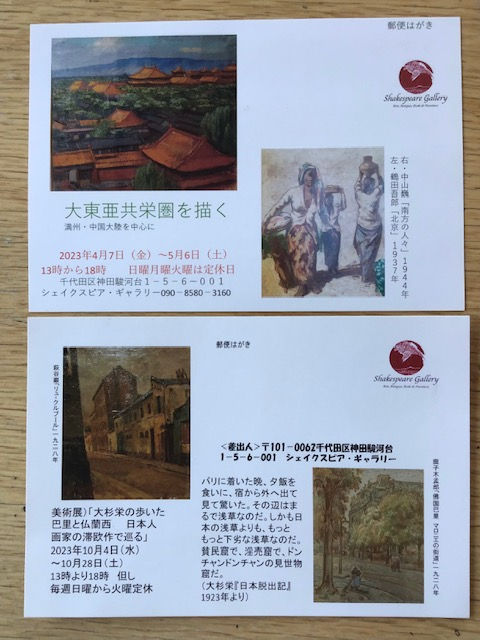
例えば「大東亜共栄圏を描く」。このテーマは戦時中に軍に動員されたり、時局的雰囲気の中で画家たちが描き残した作品を集めたものだが、私がこのブログでしばしば取り上げてきたテーマにも通じるものであり、私は強く興味を持った。また、この秋には<大杉栄とその時代>を巡る画家たちの作品を取り上げた企画があった。今年は<関東大震災から100年>ということで伊藤野枝・大杉栄らにも注目が集まったから実にタイムリーな企画であった。私自身はつい社会派のテーマに惹かれてしまうが、清水さんが取り上げるテーマは多様である。また、画廊にはそれぞれ取り扱う作品のジャンル的傾向というものがあるようだが、その点でも私はシェイクスピア・ギャラリーに期待かつ注目しているのである。(2023.10.23)

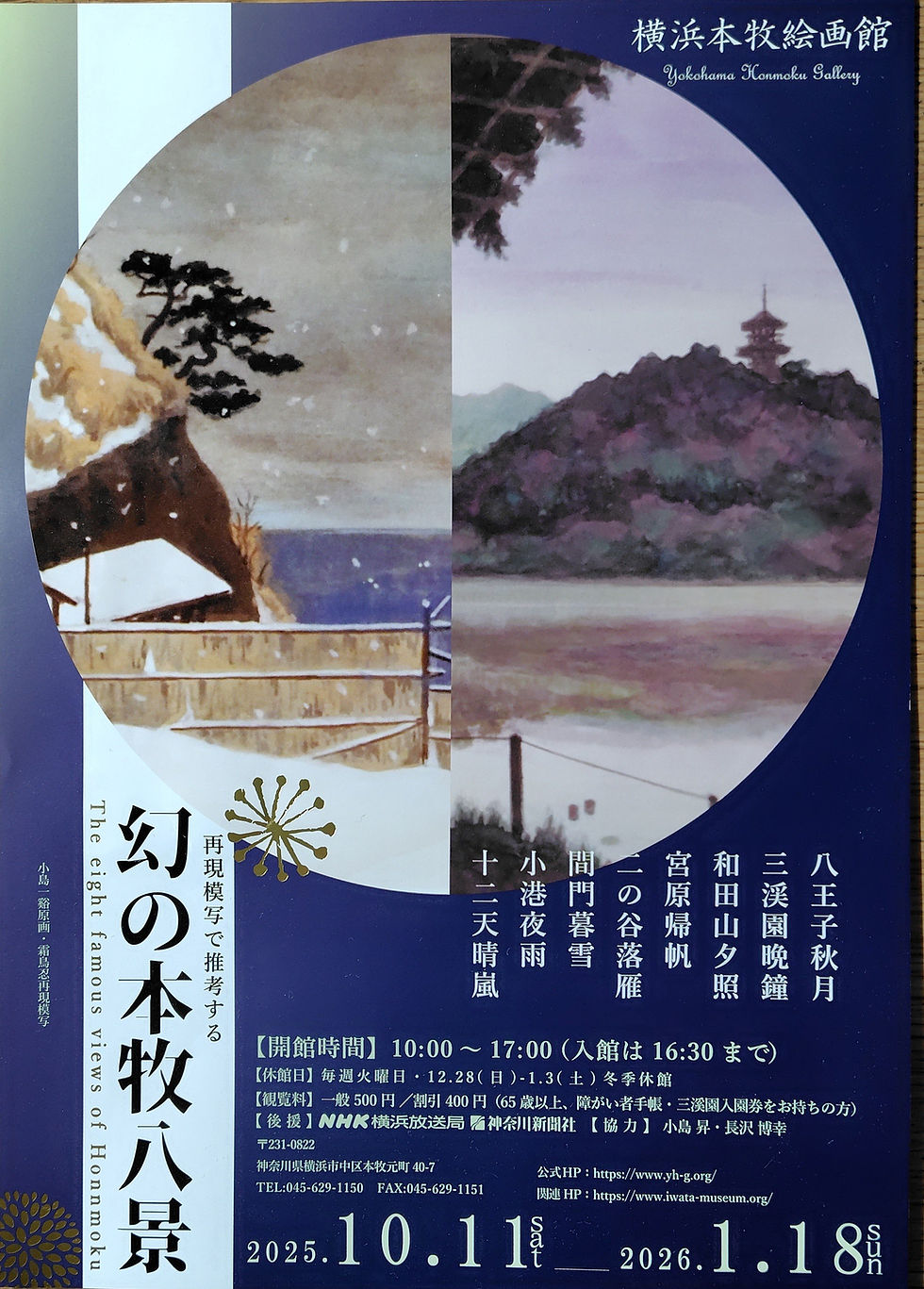

コメント