「ちひろ美術館・東京」を訪ねて
- 西村 正

- 2019年12月10日
- 読了時間: 3分

絵本画家として知られるいわさきちひろは若い頃、私の叔父・西村俊郎と同じく岡田三郎助に師事していたということを知ってから、私は東京都練馬区下石神井にある「ちひろ美術館・東京」を訪ねてみたいとずっと思い続けてきた。そしてその想いは今月になってやっと叶えることができた。そんなに遠い場所ではないのに延ばし延ばしになっていたのはなぜかと考えてみると、私はどうも水彩画というものの良さをよく理解していなかったからのように思う。
いわさきちひろ(1918—1974)は14歳から17歳までの四年間、岡田三郎助の画塾で学んだ。そして17歳のとき、当時女流画家の登竜門とされた朱葉会の公募展で入選している。祝賀会での記念写真を見ると、前列左端には岩崎ちひろが、2列目には審査員の有島生馬、藤田嗣治、小寺健吉らが写っている。実は私はちひろの油彩画を期待して「ちひろ美術館」を訪ねたのだが、残念ながら油彩画を見ることはできなかった。ちひろは戦後の1947年になって画家として生きていくことを決意したという。そして彼女が選んだのは水彩画だった。私はこれまで、ほとんど「ちひろカレンダー」でしか彼女の作品に接してこなかったのだが、この美術館に来て改めて彼女の作品を見ていくと、これまであまり考えたこともなかった水彩画の魅力とその可能性に気づかされた。館内の図書室では、ちひろに縁のある人たちがビデオレターのように5分程度語る映像を見ることができる。そこで私は久々に松本善明さんに会い、その声を聞いた。もう50年も前のことだが、私が通っていた高校は善明さんの選挙区にあったので、私は彼の顔も声もよく知っていた。当時は革新勢力が強い時代だったし、松本善明という人は共産党支持者の枠を超えて保守派からも絶大な人気のある人だったように思う。その善明さんが、ちひろの夫なのであった。

※朱葉会の写真は、石内都著「都とちひろ」p.91を接写させていただきました。
いわさきちひろの作品については今さら私が説明するまでもないだろう。むしろ私のほうが彼女の作品に対する根強い人気について、これまでよく知らなかったのだ。ミュージアムショップで見つけた『ちひろ美術館ものがたり』(松本由理子著、2003年、講談社+α文庫)を読むと、ちひろの死後、遺族が美術館建設を決意して、その計画をどのように実現させて今日に至ったかがよく分かる。そして松本家の文化資本というか、人脈の豊かさに圧倒される。飯沢匡、黒柳徹子、山田洋次、その他大勢の著名な人たちが実質的に協力しているのだ。ちひろ作品が持つ魅力と作品が放つ力が多くの人たちに認められているからだろう。
実は西村俊郎も少数ながら水彩画を残している。馬などを色紙に描いたものだが、残念ながら保存状態が良くない。水彩画は油彩画に比べて作品管理が遥かに難しそうに思われる。膨大な数のちひろコレクションの管理はさぞかし大変な仕事だろう。ピエゾグラフという方法によって水彩画のデジタルアーカイブを作る技術が存在することも、私はこの美術館を訪れて初めて知った。安曇野ちひろ美術館にも行ってみたいし、「ちひろ美術館」からはこれからまだまだ多くのことを学ばせてもらえそうだ。 (2019.12.10)

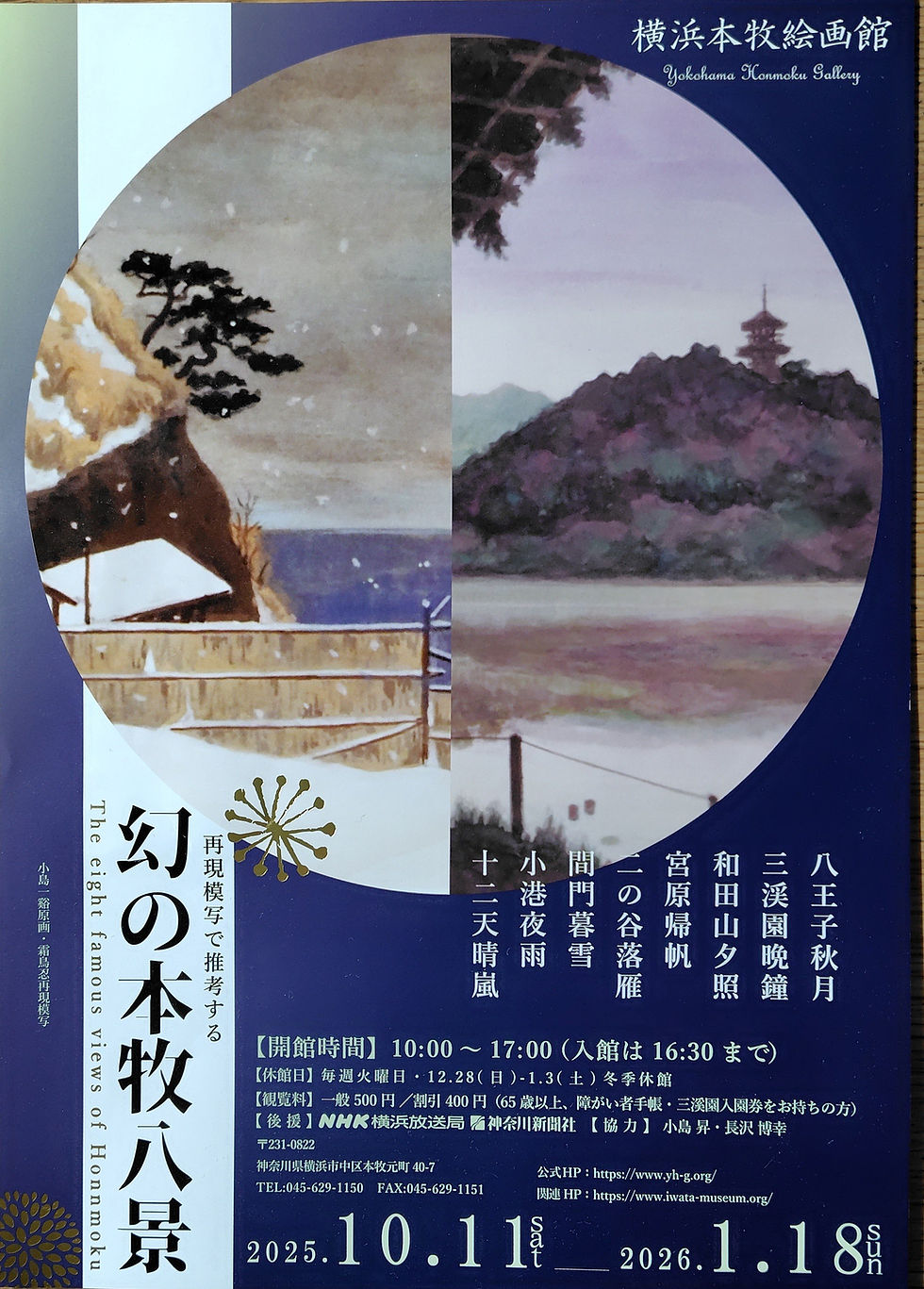

コメント