東京国立近代美術館所蔵の戦争記録画を観る
- 西村 正

- 2025年9月26日
- 読了時間: 5分

この展覧会がこの夏に開かれたことには本当に意味があると感じる。私は八月中旬に同館を訪れたのだが、展示物の数は短時間では見切れないほどあり、私は近いうちにまた来る決心をして閉館間際の会場を後にしたのであった。新聞やテレビをはじめとする多くのメディアにも取り上げられて来たので、時間が経つほどに観たものが頭の中で整理されていくのを感じている。私の叔父・西村俊郎もあの時代を生きてきた画家の一人だから、戦争と芸術というテーマは、このブログでも何回も取り上げてきたが、私にとっても避けて通れないものなのである。
一口に戦争画といっても、描かれたテーマは様々である。戦闘場面が全てではない。また、キャンバスに描かれたものが多いのは当然としても、ポスターや絵葉書なども時代の記録として展示されている。まず眼を引いたのは満蒙開拓団への参加を呼び掛けるポスターである。もちろん画家による原画があったことは言うまでもない。左下に担当省庁として「拓務省」の文字が見える。満洲への開拓移民として移住した人は27万人と言われる。日本の敗戦とソ連軍の侵攻によって、引き上げの途中で多数の命が失われ、多くの中国残留孤児を生み出したことは周知のとおりである。

戦争当時はあらゆるものが国家による統制下に置かれ、画家についても戦争遂行に協力的でない者には絵の具の入手すら困難にされたのだから、制作活動を続けるためには積極的であれ消極的であれ何らかのポーズを取ることを余儀なくされたのである。同館の展示物を観るとそのことがよく判る。例えば小磯良平の「娘子間(ジョウシカン)を征く」は中国山西省にある万里の長城の名所・娘子間を進軍する日本軍の兵士たちを描いたものだが、戦闘場面ではない。しかし異国情緒あふれるこのような奥地にまで日本軍が進軍していることを伝えることには大きな意味があっただろう。フィリピンにおける米軍の降伏後の日米会見を描いた宮本三郎「本間、ウエンライト会見図」も日本軍の勝利を誇示する強いメッセージ性も持っていたに違いない。この作品では会見を記録・撮影するスタッフの存在がクローズアップされていることも特徴的である。宮本にはシンガポールにおける英軍の降伏後の日英会見を描いた「山下パーシバル両司令官会見図」もある。
さて西村俊郎が戦時中に横須賀海軍基地で他の画家たちと一緒に作品を制作していたという話を当ブログで以前に紹介したことがあったが、叔父の師であった岡田三郎助、藤田嗣治、中村研一の三人も戦争記録画に関わっていたことはよく知られている。特に藤田と中村は戦地に派遣された画家たちの中心的な存在として戦闘場面を描いた作品を多く残している。藤田については以前に取り上げたのでここでは繰り返さないが、その作品が持つ迫力が圧倒的なものであることは今回も際立っていた。真珠湾攻撃の直前に敢行されたマレー半島コタバル上陸作戦を描いた中村研一「コタ・バル」も相当な迫力である。



次に、伊原宇三郎「特攻隊内地基地を進発す(一)」を紹介しよう。この作品は戦争末期になって、ついに「特攻作戦」と呼ばれたものが始まったことを描いているが、日の丸を振って万歳を叫ぶ人々の中で一人の女の子がこちらを振り向いて睨んでいる姿が描き込まれている。画家のささやかな、せめてもの抵抗の気持ちだったとも考えられようか。


西村俊郎は戦地に行くことはなかったが、横須賀海軍基地内にいたのだから、ある意味お互いに監視されているような環境の下で戦争記録画とされる作品を制作していたであろうことは想像に難くない。と言うのは、西村俊郎のその当時の作品は全く残されていないし、本人も具体的な話をしなかったからである。作品は廃棄されたのかもしれないし、どこかに残っているのかもしれない。東京国立近代美術館における今回の展覧会出品作品の多くは戦後米国に移送されていたものが「無期限貸与」されて同館に収蔵されたものである。戦争記録画には常に戦争責任の問題が付きまとう。ゆえに画家たちが自らの戦争記録画作品を誇らしげに語ることはまず無かろう。しかし、制作依頼者の意図とは別に、画家たちがそこに実験的とも言える活躍の場を見出そうとした可能性は否定できないだろう。それだけに、戦争記録画に対する評価は複雑である。なお、同展には戦後のコーナーもあって、その中の一つが丸木位里・俊「原爆の図」である。さらに、当ブログの記事の中でも閲覧者が際立って多い浜田知明「初年兵哀歌(歩哨)」とも久々に対面できたことを付け加えておこう。(2025.9.26)
■同展を構成する8つのコーナー:
「1章 絵画は何を伝えたか」
「2章 アジアへの/からのまなざし」
「3章 戦場のスペクタクル」
「4章 神話の生成」「
「5章 日常生活の中の戦争」
「6章 身体の記憶」
「7章 よみがえる過去との対話」
「8章 記録をひらく」
◆会期は10/26(日)まで

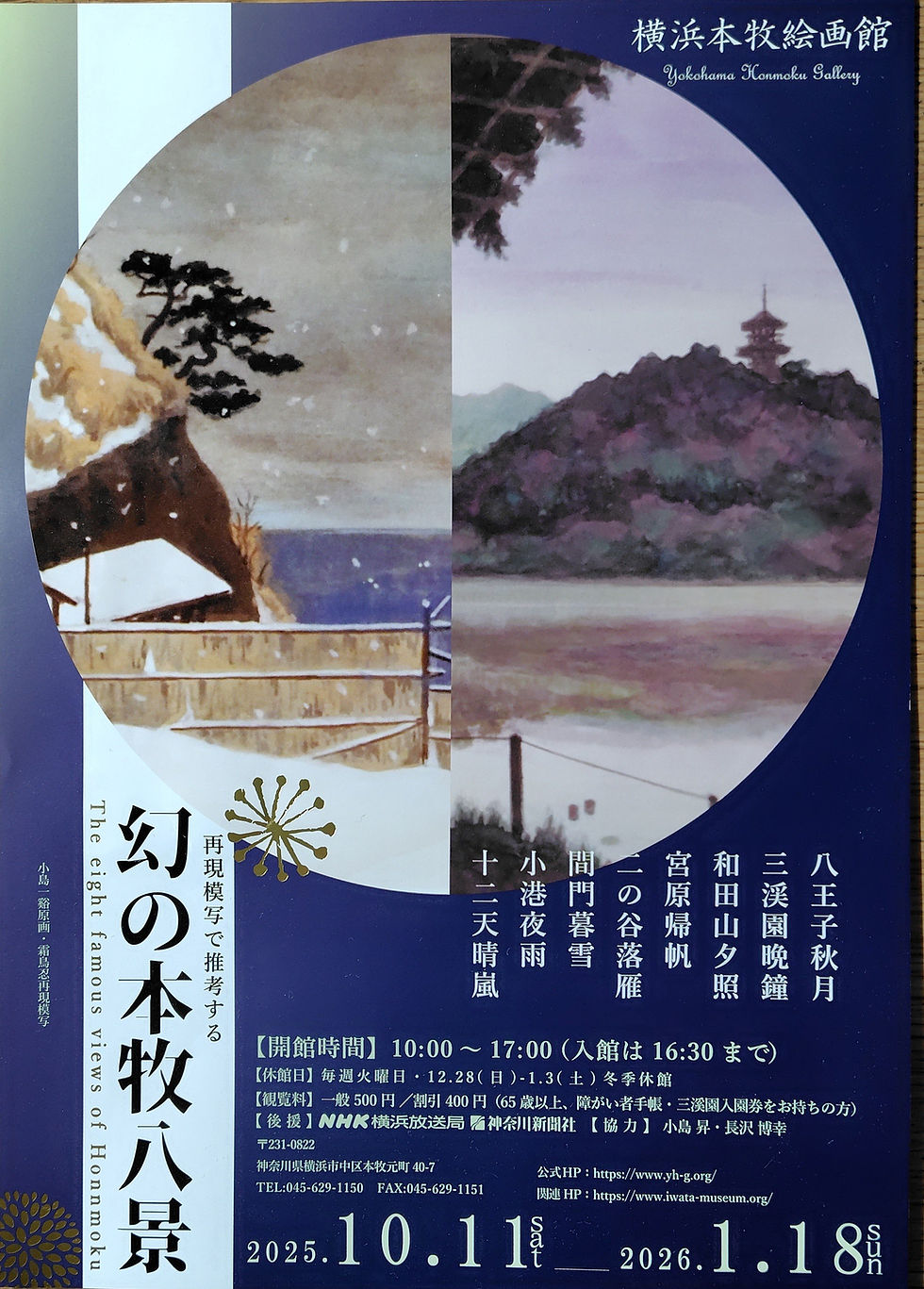
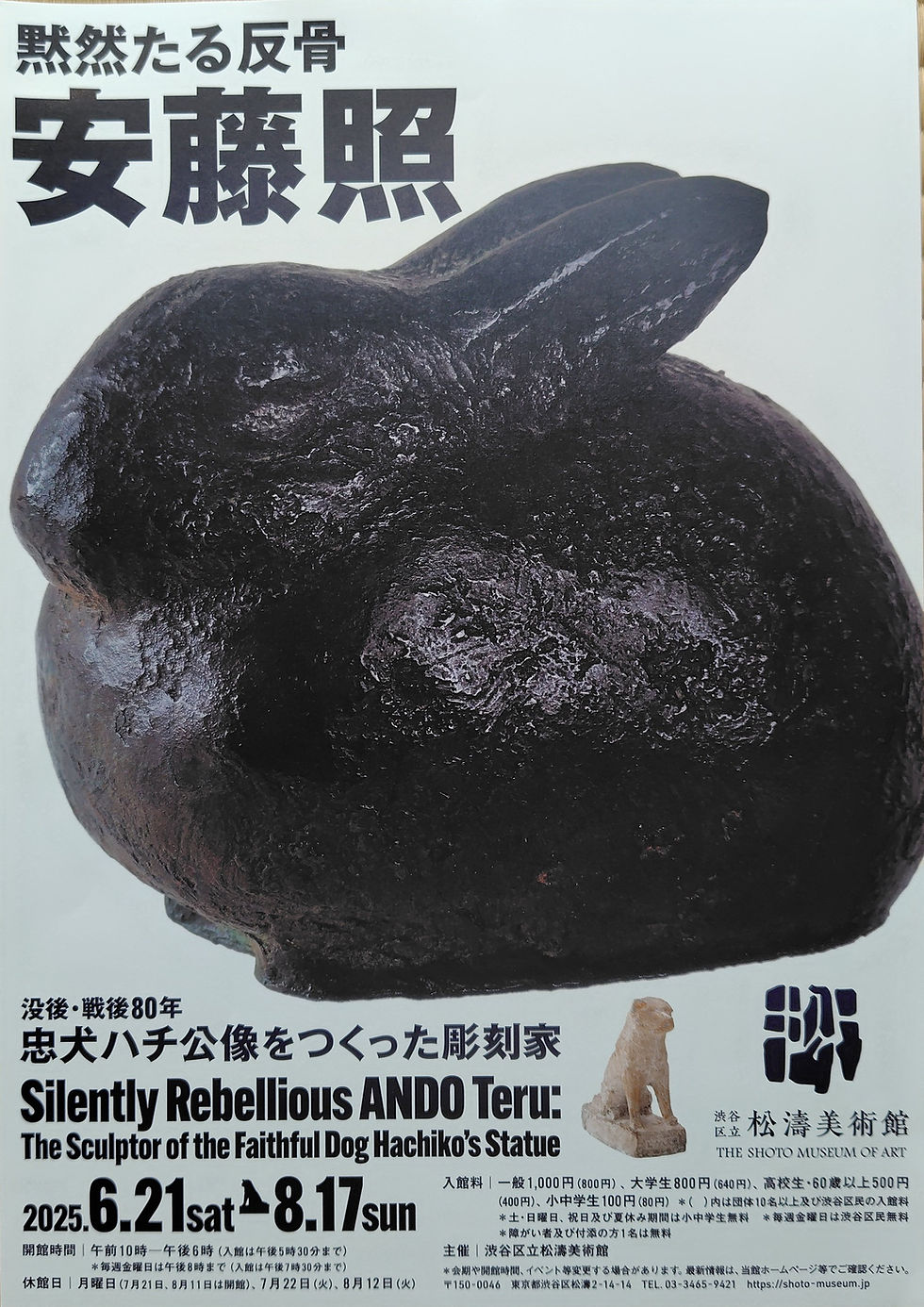
コメント