「田中一村と刑部人」展を観て
- 西村 正

- 2019年3月17日
- 読了時間: 2分
更新日:2021年2月2日
早春の一日、栃木市に「とちぎ蔵の街美術館」を訪ねた。日本画家・田中一村(1908~1977)と洋画家・刑部人(1906~1978)はともに栃木市ゆかりの画家であり、生年と没年もほとんど重なっている。二人とも私の好きな画家だが、私が興味を感じたのは、この展覧会が「田中一村と刑部人---希望と苦悩のあいだ---」と題して開かれたことである。

とちぎ蔵の街美術館
田中一村については奄美大島で描いた作品の展覧会を横浜で観たことがあった。彼は最初は中国風の絵を描いて人気を博していたのだが日中関係の悪化とともに需要がなくなり、画風を変えざるを得なかったのだという。今回の展示は奄美に渡る前の作品だが、その絵の中にもすでに後の画風への萌芽が見られるように思えた。
刑部人については、解説文の中に「1920年代のパリで新しい芸術を学んだ画家たちが帰国し活躍する中で、師の和田英作から『これからの時代は個性的な絵を描かなければ帝展入選も危なくなる』と言われ、一時期スランプに陥りました」と書かれていることに目が留まった。刑部人でもスランプがあったのか!というのが私の正直な感想だが、同時に、私の叔父・西村俊郎が晩年に書いたエッセイの中で、洋行帰りの画家たちが持ち込む ”新しい芸術” を批判していたことを思い出した。また、スランプを乗り切ったとされる刑部人が “新しい芸術” に染まったふうには全く見えないことを嬉しく思った。
田中一村も刑部人も戦争の時代に生き、その画業に対して様々な制約や影響を受けてきたわけだが、刑部人の「少年通信兵」という作品の解説に「戦闘の絵は描かなかったが絵具などの支給を受けるために兵士の生活を題材とする作品を描いた」と書かれていたことが心に留まった。 (2019.3.17)

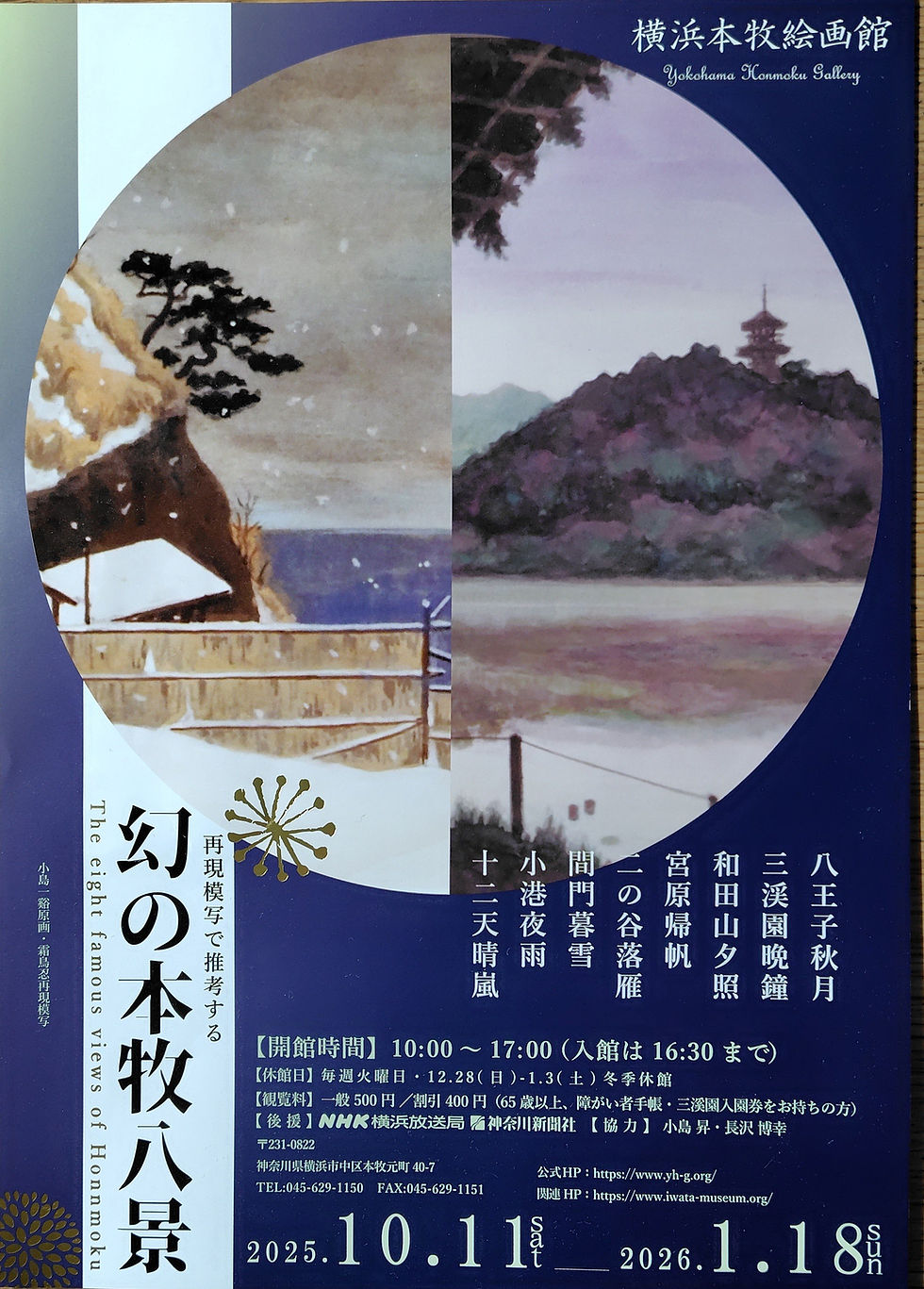

コメント