コンスタブル展
- 西村 正

- 2021年5月30日
- 読了時間: 3分
東京駅丸の内口の三菱一号館美術館「コンスタブル展」は、会期末が近づいているのに依然コロナ禍による閉館が続いている。同展は二月からやっていたのだからもっと早くに観ておくべきだったのだが、今となってはもう遅い。そこで、やむなく1500円を払ってオンラインで観ることにした。オンラインのものに金を払うのは初めての経験である。図録も購入した。


図録の表紙と、表紙に採用されたコンスタブルの作品「モルヴァーン・ホール、ウォリックシャー」(※図録p.67を接写させていただきました。)
西村俊郎は晩年のエッセイの中で次のように書いている。
「大阪で万国博覧会が開かれたとき、会場の中に美術館ができた。陳列作品は日本の有名画家の油彩画が多かったが、私はその最後の方にすばらしい絵を見つけた。切り割りの山と水が前景で、中景の野原に教会や民家が描かれた、あまり大きな絵ではないが、私はその絵に感動した。作者は英国のコンスターブル。名前は兼ねてから知っていたが、絵を見るのは初めてだった。私の絵の進路はこれだと感激した。このとき、私の進むべき道は決まった。後年ロンドンのテムズ河畔のテート美術館でたくさんのターナー、コンスターブルの絵を見たが、どの風景画も空気の満ち満ちたものであった。この二人の画家は、いずれも完璧にヴァルールをマスターしている。」(西村俊郎「私の絵画ノート---特に、ヴァルールについて---」より引用 )
大阪で万国博覧会が開かれたのは1970年。そのとき叔父は61歳である。私は高校3年生であったが叔父に薦められて、しかも叔父が費用をもってくれて夏休みに京都と大阪に一人旅をしたことは、このブログの最初のほうに書いたとおりである。その数年後に叔父は一念発起して渡欧する決意をしたのだから、コンスタブル作品との出会いは叔父にとって重大な契機になったものと思われる。そのとき叔父が観た絵がこの図録の表紙に採用された作品だったかどうかは定かでないが、この「モルヴァーン・ホール、ウォリックシャー」という作品は20号(M)程度の大きさだから「あまり大きな絵ではないが」という記述に当てはまるものではある。
今回は残念ながらオンラインでの鑑賞と家に届いた展覧会図録を見ただけで、実際の作品を目の当たりにすることはできなかったが、インターネット上で調べられる限り、私はコンスタブルとターナーの作品を見比べてみた。ターナー(1775—1851)とコンスタブル(1776—1837)は同時代を生きた二人だが、今回の展覧会でも「対決」という捉え方で比べられているものの、二人の画風にはかなり違いがあるようだ。ターナーの変幻自在さに対して、コンスタブルはずっと守備範囲が狭いように感じられる。そして、叔父は明らかにコンスタブルのほうに親近感を感じていたに違いない。
ターナーやコンスタブルが活躍した今から約200年前の時代、彼らの画風は革新的なものであったという。彼らの中にすでに、その後の印象派に通じる画風が認められる。そして絵画の新しい潮流はその後も次々と現れてきた。しかし、後の時代に生きる人々が常に「最先端の潮流」に最大の価値を見出すとは限らないだろう。写実を重んじた西村俊郎が「最先端の潮流」にではなく「印象派以前」のコンスタブルの画風に自分の「進むべき道」を見つけたように、絵画における嗜好は多様化して一向に構わない、と私は思う。今回の「コンスタブル展」のキャッチコピーである≪光を描く、空気が動き出す。≫は、まさに叔父が生前に繰り返していた言葉そのものであった。 (2021.5.30)

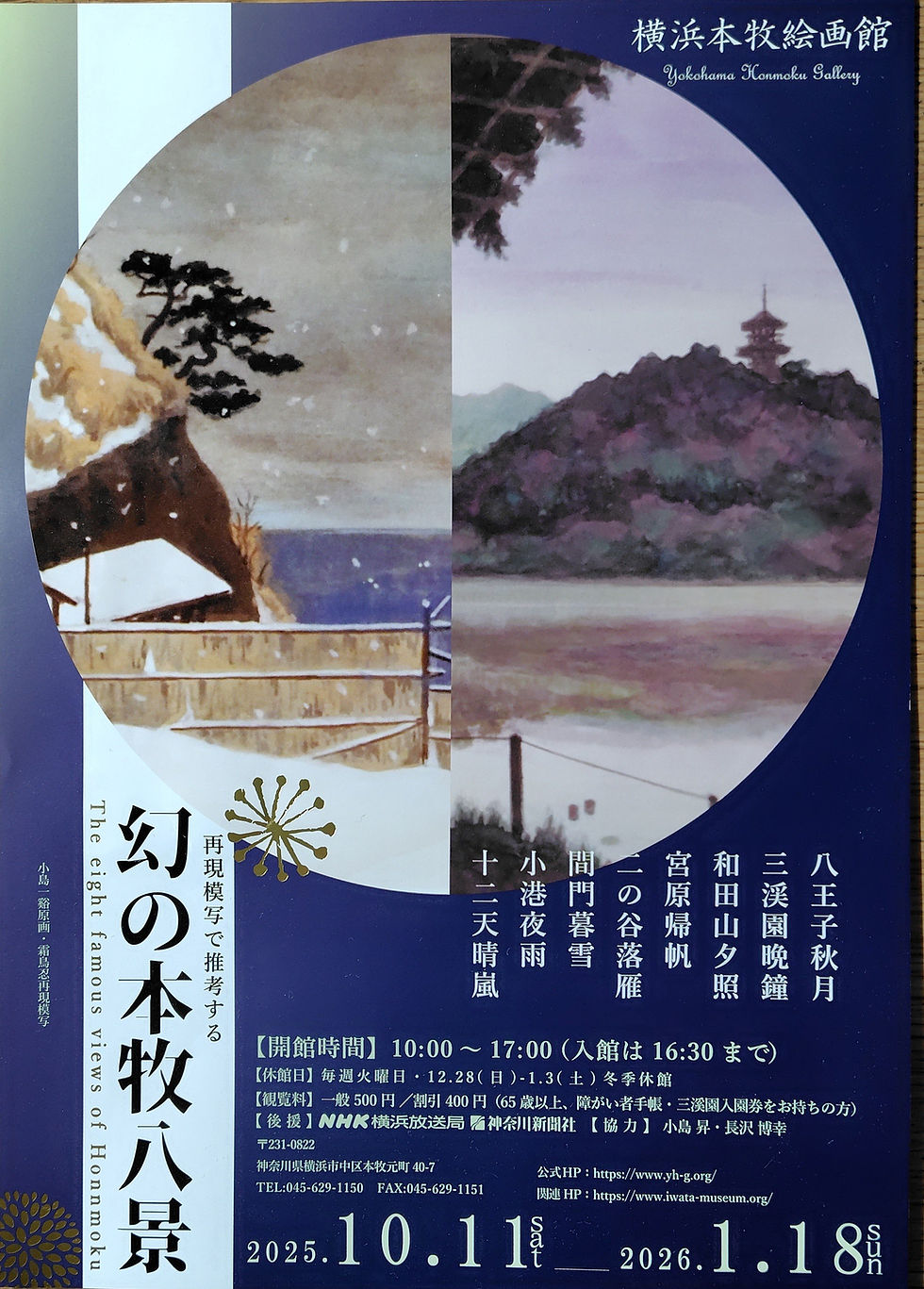

コメント