日本民藝館を訪ねて
- 西村 正

- 2020年10月25日
- 読了時間: 2分
秋の一日、以前から一度行ってみたかった日本民藝館を訪ねた。井の頭線の「駒場東大前」駅から徒歩5分ぐらいのところにある。同館の創設者は柳宗悦(1889—1961)である。「民衆的工芸」の略語である「民藝」は柳や、その賛同者である河井寛次郎、濱田庄司らが提唱した概念で、職人の手仕事による日用工芸品が持つ美を重視する。彼らと交流があったバーナード・リーチも民藝運動の推進者の一人であった。


その日はちょうど「アイヌの美しき手仕事」展の期間中であったが、併設展も見ることができた。陶画や燭台、織物や家具類などの展示品を見ると、柳らの関心は「ヤマト」文化の枠を越えて、樺太や北海道のアイヌ、琉球、台湾、朝鮮、そして中国にも及んでいたことがわかる。
柳らが、芸術作品としてではなく日用品として作られたものの中に美を見出し、それを「民藝運動」として提唱したことを知ったとき、私はそこに新鮮な驚きを感じたことが忘れられない。生活に根ざした身近なものの中に美を見出した審美眼に感激したのだ。もう40年以上も前のことである。
ミュージアムショップに並べられたものの中に、イギリスのスリップウェアの影響を受けたと思われる小鉢を見つけ、思わず嬉しくなって買ってきた。島根県松江市の湯町窯の作品だが、後で解説を読むと「…かつてこの地を訪れた河井寛次郎、濱田庄司、バーナード・リーチの各師に学んだ…」とあった。この小鉢を家に持ち帰ってどう使おうか、と考えただけで楽しい気分に浸ることができた。 (2020.10.25)

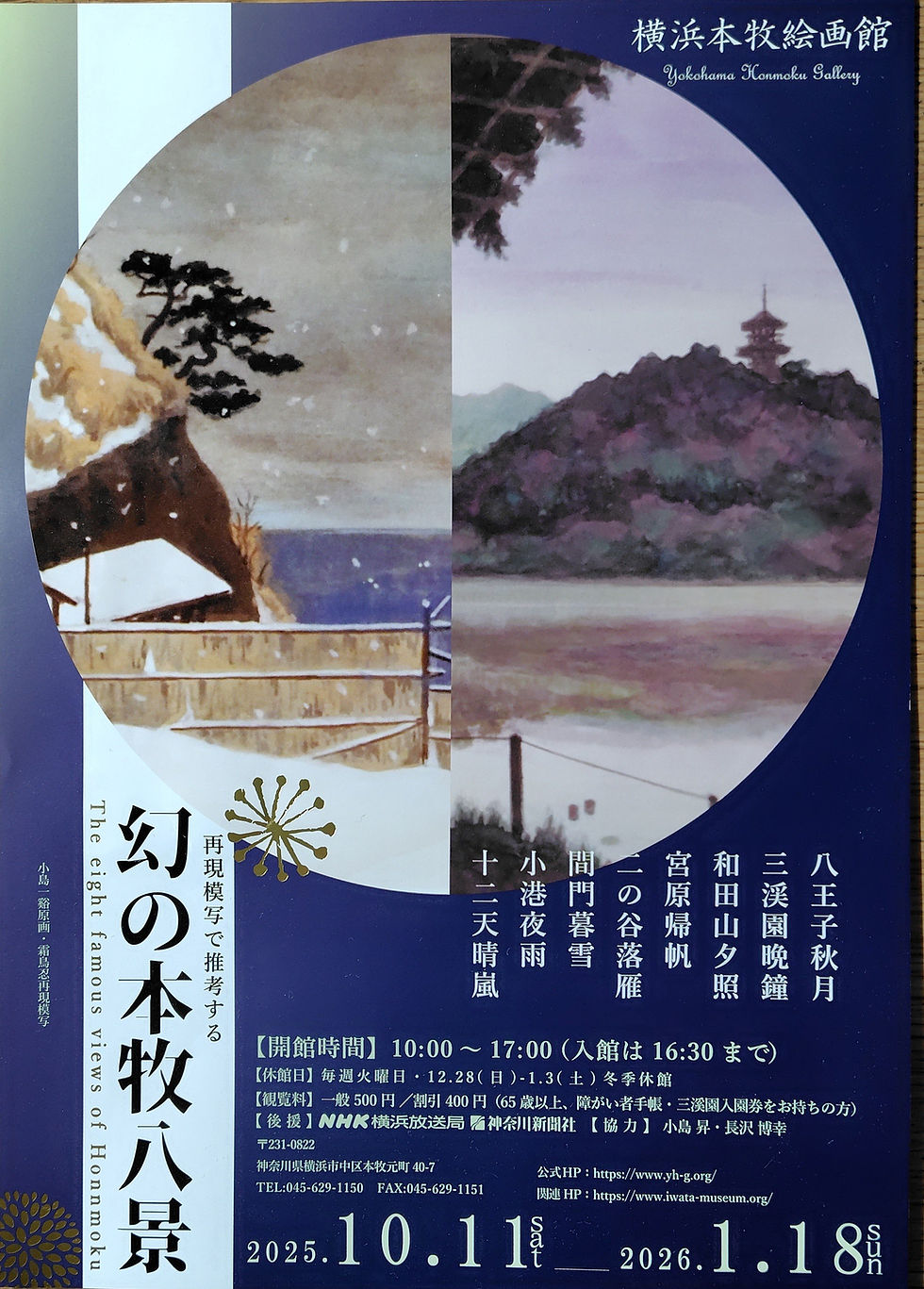

コメント