武蔵野市立吉祥寺美術館(岡田紅陽展)を訪ねて
- 西村 正

- 2020年9月1日
- 読了時間: 3分
更新日:2021年1月22日


(同館の図録『岡田紅陽 富士望景 武蔵野から』を接写)
先日、友人に誘われて武蔵野市立吉祥寺美術館を訪ねた。ここはちょうど二年前に小貫政之助展を観た場所である。実は今回の目的は、叔父・西村俊郎のエッセイの冒頭に登場する写真家・岡田紅陽の作品を観たかったのと、それからもう一つ、二年前にここで初めて観て二回目に今年になって銀座の画廊で再会したときに衝動買いしてしまった小貫の花の絵について同館の学芸員のかたに確認したいことがあったからでもある。
私が知っていた岡田紅陽の写真は、富士銀行(当時)の店内に掲げられていた大きな富士山の写真が唯一のものだった。今回の展覧会の図録巻頭を飾る作品【写真、左】は「1967年1月31日、吉祥寺駅南口より」の撮影だという。その当時、私は世田谷に住んでいて中学2年生であったが、それより5年くらい前までなら世田谷からもこのような富士の姿を見ることができたと記憶している。いま私は横浜市の西部に住んでいるが当地からは今でもこのような富士の姿が見られるときがある。とは言え、このような写真は撮りたくても容易に撮れるものではない。これは単なる作品というよりも、私の網膜に焼きついた日没の富士の姿そのものである。
岡田紅陽(本名、賢治郎)は1895(明治28)年生まれだから叔父よりも14歳年上である。その彼に「あなたの画には空気がある」と語りかけられた叔父は、よほど嬉しく励まされたのだろう。エッセイ『思いでのままに』の冒頭に書かれたエピソードからその気持ちが十分に感じ取れる。そこに書かれた「頬被りをし、古ぼけたカメラを首から提げた老人」に当てはまる写真を会場に発見したときは、「ああ、これか!」と思わず嬉しくなった。叔父が書いていることは本当だったのだ。

(同館の図録「語りえぬ言葉 小貫政之助」(2018年)より)
小貫のこの作品は図録の中で「油彩、ミクストメディア」と説明されていたのだが、私はこの「ミクストメディア」の意味がずっと気になっていた。そこで私は作品を持参して、同館の学芸員のかたに直接伺ったのである。結論から言えば、この作品には画家が意図したか否かは不明だが、部分的に油絵具以外のものが混ざっている可能性があるが「油彩」とみなしても差し支えないということであった。それを聞いて私は、作品に対する彼女の学芸員としての分析の厳密さに感心させられた。
ところで、油彩画にしろ写真にしろ、作品のどこを見て何に心を惹かれるかということは人それぞれにおいて違っていて一向に構わないと私は思う。誰かが書いた解説を読んで参考にするのももちろん悪くないが、解説に頼りすぎるのは良くない。むしろ自分の眼で見ていいと思うかどうか、好きかどうかということを大切にしたいと思うのである。
この展覧会は入館時に検温し終始マスクをしての作品鑑賞であった。そのあと街に出てから友人と入った飲食店でも先ず検温があり、テーブルは向き合わずに並んで座って壁を見ながら控えめな声で会話をするという、いわゆる「新しい生活様式」であった。それでも、それで多少なりとも元の生活に戻れるなら家に閉じこもっているよりはずっとマシであると感じた一日であった。 (2020.9.1)

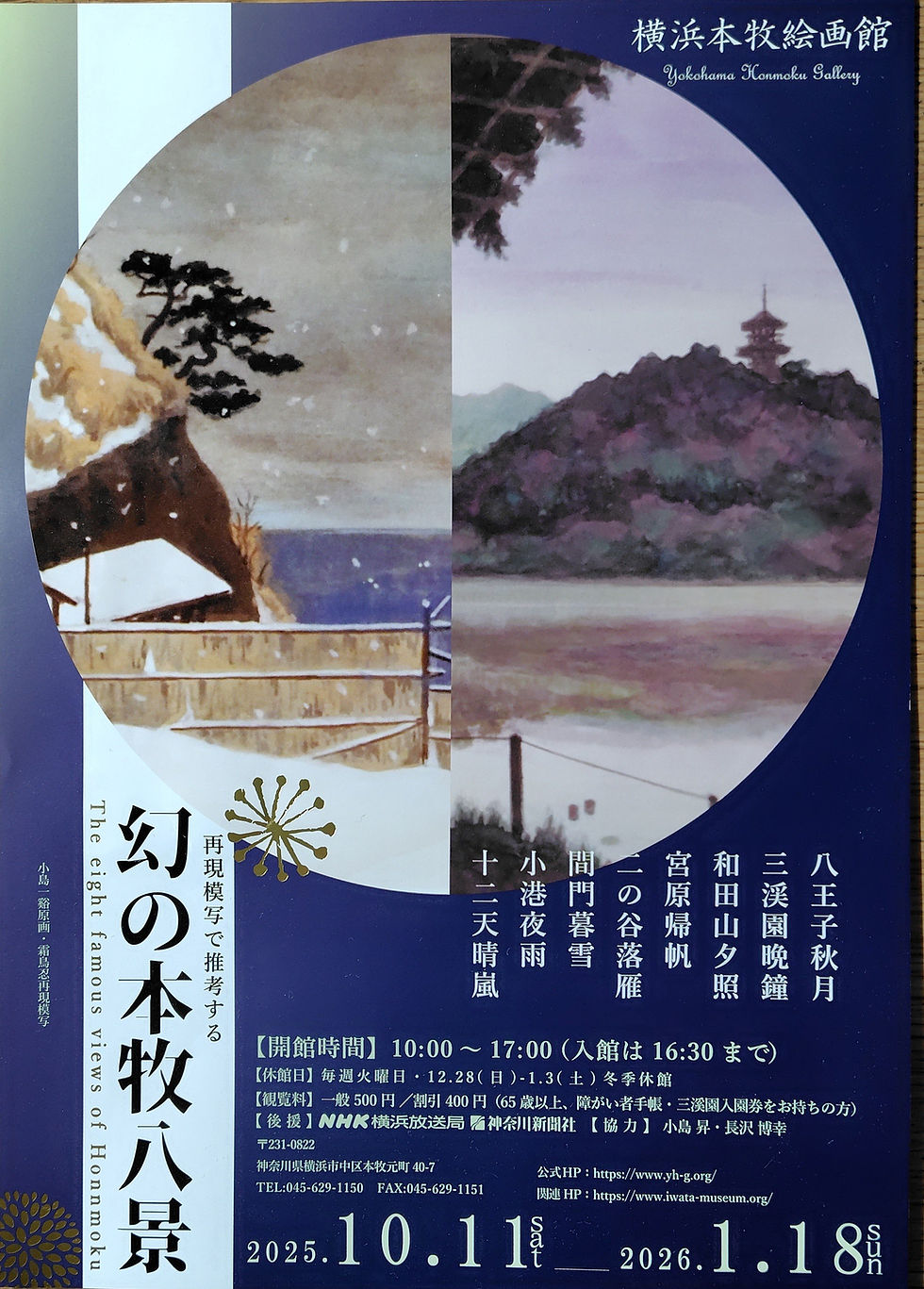

コメント